この記事では、生命保険必要か?いらない理由や見直すポイントを解説していきます。
生命保険は将来のリスクに備える方法のひとつ。
病気やケガ、死亡時などに給付金や保険金が受け取れるため、もしものときのために加入を検討している人も多いでしょう。
 ぷにこ
ぷにこ今のうちに備えておきたい!
一方で「生命保険はいらない」という意見もあるので、加入しようか迷ってしまいますよね。
この記事を読めば、生命保険が本当に必要なのか、見直すポイントがわかります。
「将来のお金の不安を減らしたい」と思っている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね♪



貯金0・借金ありからマイホームを建てるまでお金を貯めた、ぷにこがお届け!
生命保険は必要?いらないと言われる3つの理由
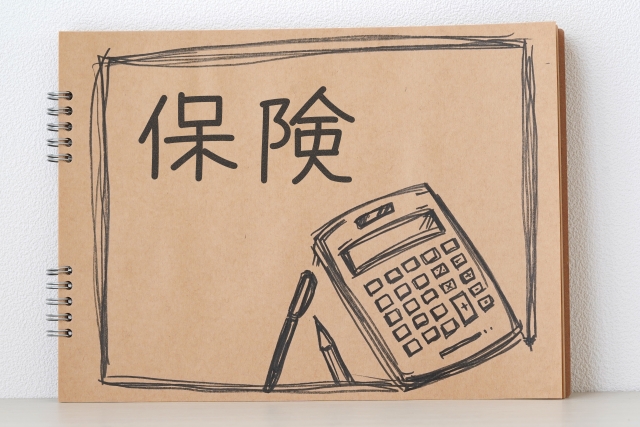
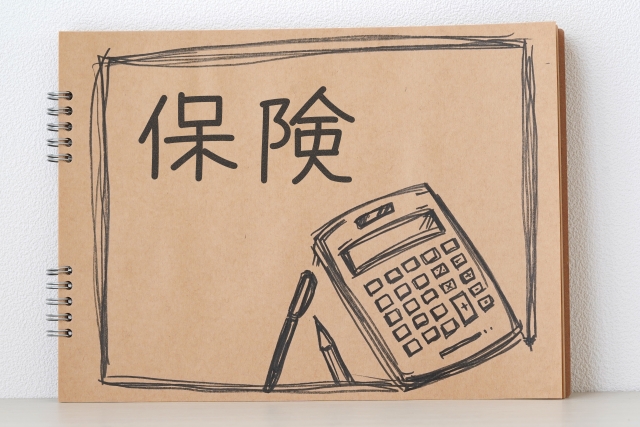
多くの日本人が入っている生命保険。
それにも関わらず、なぜ生命保険はいらないという意見があるのでしょうか?



どんな意見だろう?
今から理由を3つ紹介していきますね。
理由①国民皆保険制度が充実しているから
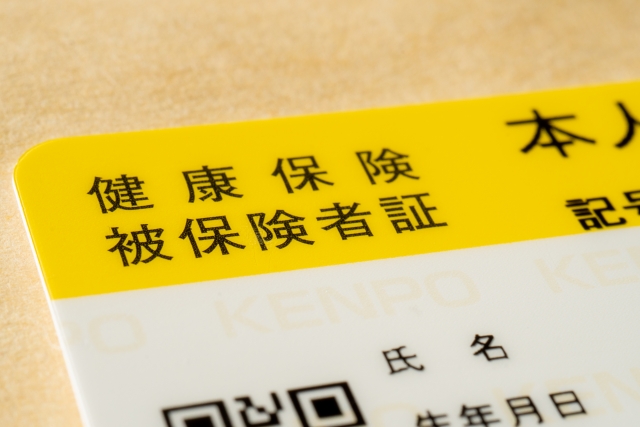
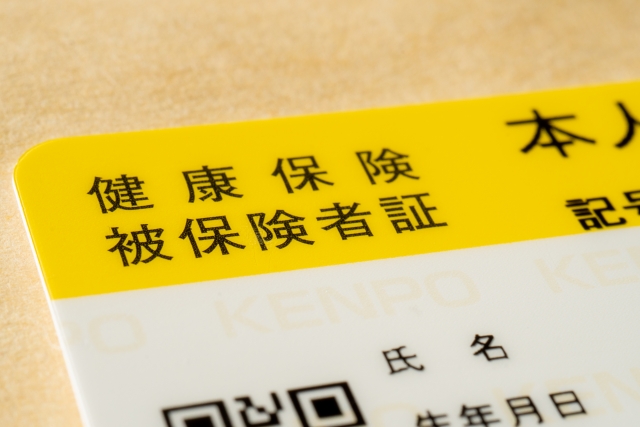
生命保険が必要ないと考える理由1つ目は、国民皆保険制度が充実しているからです。
国民皆保険制度とは?
すべての人が病気やケガをしたときに医療費の一部を公的な機関が負担する制度に加入。
そして、全員が保険料を支払うことでお互いの負担を軽減する。
これは国が保障する制度で医療費の自己負担は最大でも3割で済みます。
しかも、3割負担でも保険料が高くなった場合には、一定額以上の医療費負担は軽減される高額療養費制度があります。
高額療養費制度とは?
1ヶ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、 一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度のこと。



制度が充実しているから、生命保険はいらないと考える人もいるようだね。
理由②保険を利用する機会が少ないから
2つ目の理由は、保険を利用する機会が少ないからです。
生命保険は、死亡や重病時などに支払われるもの。
若くて健康な人は、病気や死亡リスクが低いため、保険を活用する機会が限られるのも事実です。
具体的にデータを見てみましょう。
人口10万人に対して入院の総数は1,175人で入院する確率は1.7%。
参照:厚生労働省「令和5年患者調査」



20〜30代で見ると、もっと確率は下がるよね!
40歳男性の死亡者数は男性で1,000人につき1人。女性は0.59人とのこと。
参照:厚生労働省「令和5年簡易生命表」
生命保険は、おもに死亡したときや病気・ケガを治療したときに保険金や給付金を受け取ります。
しかし、上記の統計を見てみると、実際に自分が使う可能性は低いと考える人もいるようです。
理由③十分な貯蓄でまかなえる場合があるから


3つ目の理由は、十分な貯蓄でまかなえる場合があるからです。
生命保険の目的は「万が一のときに経済的な負担を軽減する」こと。
しかし、すでに十分な貯蓄がある場合は、わざわざ保険で備える必要がないとも言えるでしょう。



それに今は共働き世帯も増えているよね!
さらに、会社員なら健康保険などの公的保障もあります。
そのため、「毎月保険料を払うよりも、貯蓄と公的保障で備えたほうが合理的」と判断する人もいるのです。
- 万が一、病気やケガで長期間働けなくなったら?
- 貯蓄を切り崩してしまい、老後資金が足りなくなるかも?
- 自分に本当に合った保険の選び方がわからない…
万が一のときに本当に乗り切れるか知りたい人は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談してみるといいですよ!
必要以上の保障に加入して家計を圧迫したり、逆に必要な保障が不足していたり…。
こんな事態を避けるため、あなたのライフステージと家族構成にあわせて、必要な保障と家計の負担のバランスを最適化してくれるFPさん。



適切な保険選びは、家計のゆとりと将来への安心につながっているよ!
自分だけで考えるのが不安な人は、お金のプロFPさんに相談してみてください!
\オンラインで相談無料/
生命保険の見直すポイントを紹介


生命保険はライフステージや経済状況によって必要な保障が変わるため、定期的に見直すことが重要です。
ここでは、見直しの際にチェックすべき4つのポイントを紹介します。
ポイント①必要な保障内容を確認する
1つ目のポイントは、必要な保障内容を確認することです。
生命保険にはさまざまな種類や特約があり、すべての保障が自分に必要とは限りません。



以下では、生命保険の種類や必要な人を紹介するね!
| 生命保険 の種類 | 概要 | 必要な人 |
|---|---|---|
| 死亡保険 | 自分が亡くなった場合、 家族にお金を残すための保険 | 扶養している家族 (配偶者・子ども)がいる人 |
| 医療保険 | 入院・手術などの医療費を サポートするための保険 | 貯蓄が少なく、 医療費に不安がある人 |
| 介護保険 | 要介護状態になったときに 給付金がもらえる保険 | 将来、介護費用を 準備したい人 |
保障内容を見直せば、月々の保険料を節約できる可能性もあります。
無駄な保障を省き、本当に必要な保障だけを選んでいきましょう。
ポイント②保障期間を確認する


3つ目のポイントは、保障期間を確認することです。
保険の保障期間には大きくわけて「定期型」と「終身型」の2種類があります。



それぞれの特徴は以下の通り♪
| 保障期間 | 特徴 |
|---|---|
| 定期型 | 一定期間だけ保障が続くタイプの保険。 保険料が割安だけど、更新時に保険料が上がる。 |
| 終身型 | 一生涯保障が続くタイプの保険。 保険料は高めだけど、値段は変わらない。 |
定期型は、子どもが独立するまでの間だけ死亡保障がほしい人や保険料を安く抑えたい人に向いています。
一方で、終身型は老後のリスクが不安な人や万が一のことに備えておきたい人におすすめです。
ライフステージにあわせて見直し、自分にぴったりの保険を選びましょう!
ポイント③保険料の支払いが続けられるか確認する


3つ目のポイントは、保険料の支払いが続けられるかです。
生命保険に加入すると、基本的に長期間は保険料を支払い続けることになります。
しかし、家計の状況が変わったり収入が減ったりすると、毎月の保険料が負担になる可能性もあるでしょう。



支払いが続けられるかチェックするポイントは?
| ポイント | 概要 |
|---|---|
| 保険料を手取り収入 5~10%以内に収める | 手取り月収30万円の場合、 無理なく払える保険料の目安は1.5万円~3万円以内 |
| 保険が家計を圧迫して いないかを確認する | 月々の固定費(家賃・光熱費・通信費)を見直す |
| 支払えなくなったとき の対策を知っておく | 保険を見直したり、一時的に支払いを停止したりする |
生命保険は長期間の支払いが必要なため、「無理なく支払える金額かどうか?」を慎重に判断しましょう。
でも、毎月いくら貯金すればいいの?
貯金しなきゃと思いつつ、なかなか貯められない…
と気になっている人もいるのではないでしょうか?



詳しい内容は下記の記事で解説しているので、チェックしてみてね◎
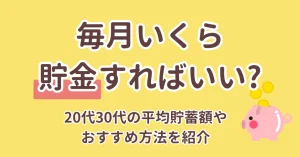
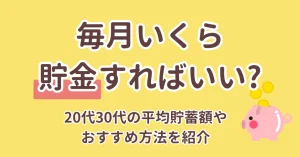
ポイント④専門家に相談する


ここまで、生命保険の見直しポイントを3つ紹介してきました。
それでも「何から始めればいいかわからない…」という人は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのもおすすめです◎
FPさんとは個人・家族の生活設計や資産運用をサポートしてくれるお金の専門家です。
保険分野で相談すると、こんなメリットがありますよ。
- 自分に必要な保障内容がわかる
- 自分に適切な保障額がわかる
- 複数の保険会社の商品を比較できる
「自分に必要な保障内容がわからない」
「もう少し保険料を抑えたい」
という方は、FPに相談することで具体的な道筋が見えてくるでしょう。
オンラインでも相談可能なので、忙しい方でも気軽に利用できますよ♪



家事や子育てで忙しいからすごい助かる!
少しでも疑問や不安があるなら、お金のプロであるFPに生命保険の相談をしてみてください♪
\オンラインで相談無料!/
生命保険必要か?まとめ
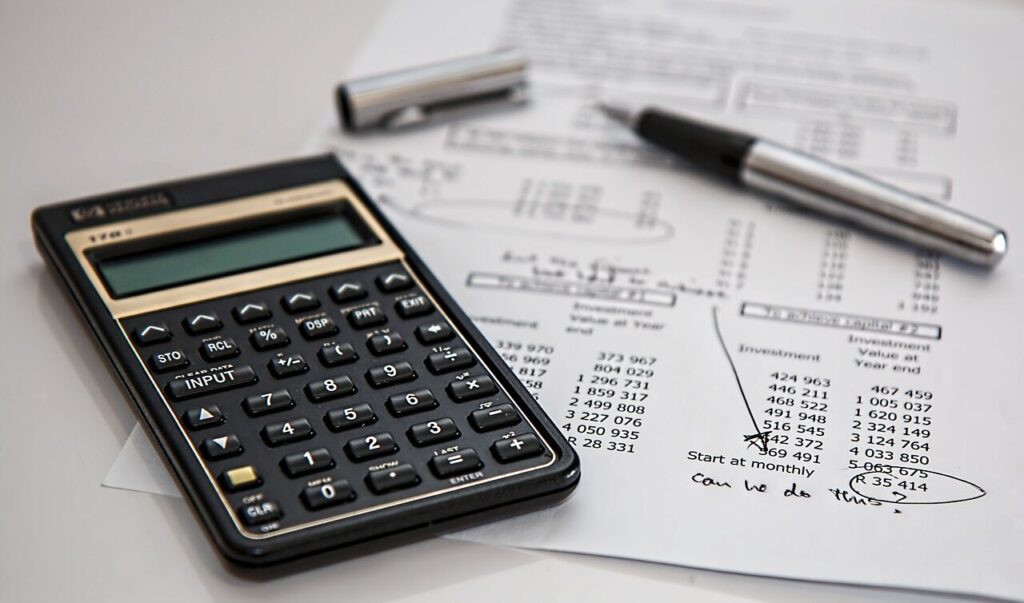
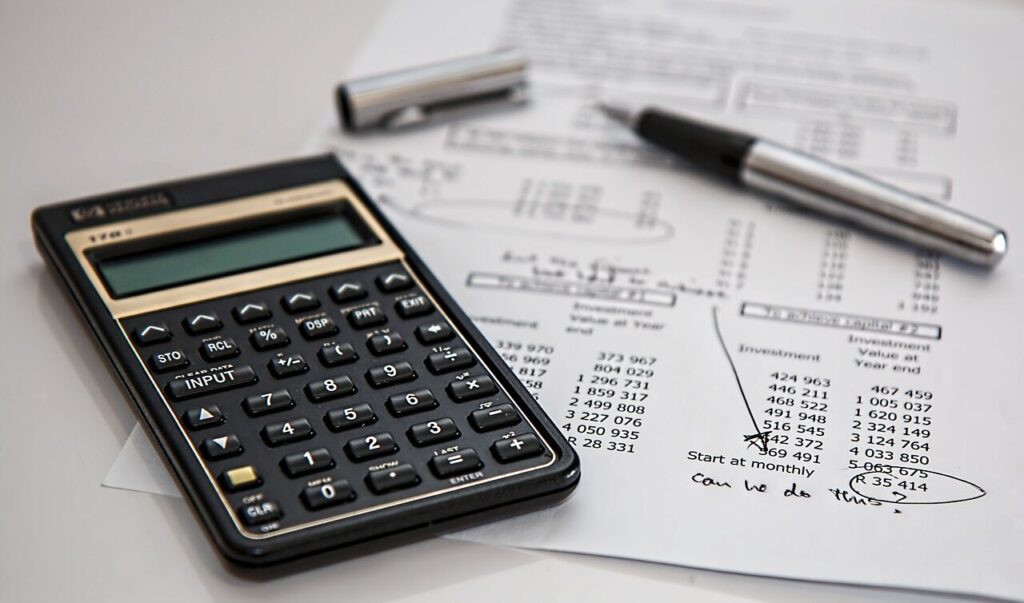
この記事では、生命保険必要か?いらない理由や見直すポイントを解説してきました。
ここで簡単に振り返っていきましょう。



まずは、生命保険がいらないと言われている理由から!
- 国民皆保険制度が充実しているため
- 保険を利用する機会が少ない
- 十分な貯蓄でまかなえる場合があるため
次に、生命保険の見直すポイントを4つ振り返っていきましょう。
- 必要な保障内容を確認する
保障内容を見直すと、月々の保険料を節約できる可能性がある。 - 保険料の支払いが続けられるかどうか
手取り収入の5~10%以内に抑える。 - 保障期間を確認する
子どもが独立するまでの保障なら「定期型」、老後の資金準備なら「終身型」の保険が向いている。 - 専門家に相談する
FPに相談すると、自分に最適な生命保険が見つかる。
自分にとって最適な保険を選ぶために、お金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのも良いですよ!
FPさんが保険分野でサポートしてくれる代表的な内容はこちらです。
- 自分に必要な保障内容を教えてくれる
- 自分に適切な保障額をいっしょに考えてくれる
- 複数の保険会社の商品を比較できる
必要以上の保障に加入して家計を圧迫したり、逆に必要な保障が不足していたり…。
こんな事態を避けるため、あなたのライフステージと家族構成にあわせて、必要な保障と家計の負担のバランスを最適化してくれるFPさん。



適切な保険選びは、家計のゆとりと将来への安心につながっているよ!
自分だけで考えるのが不安な人は、お金のプロFPさんに相談してみてください!
\オンラインで相談無料/
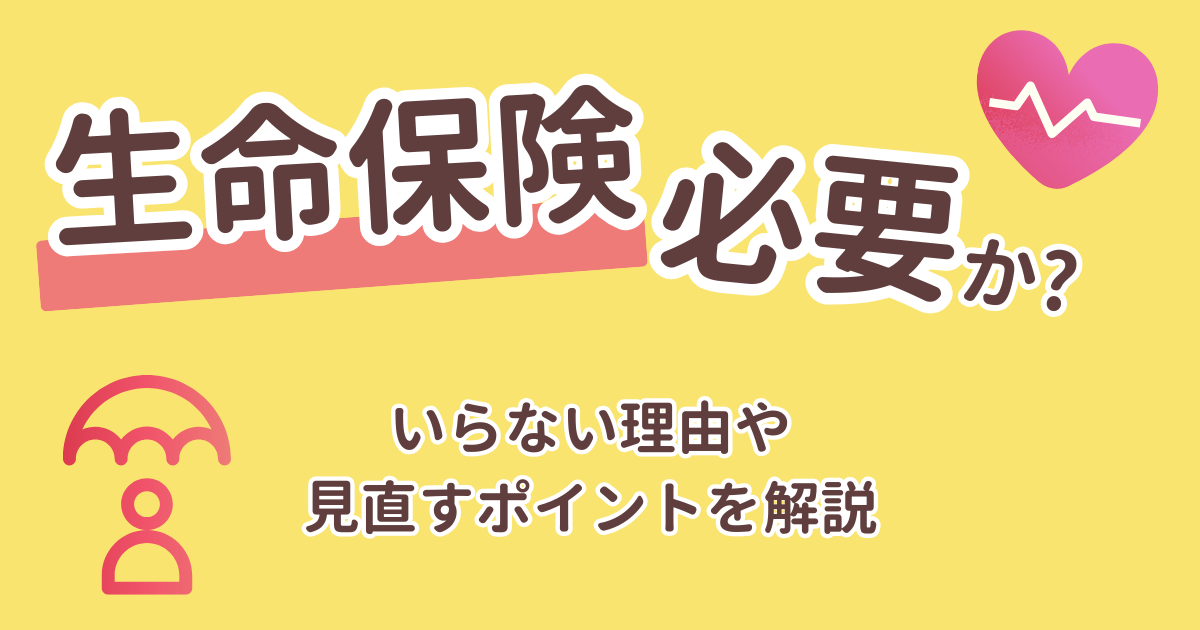
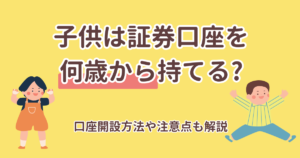
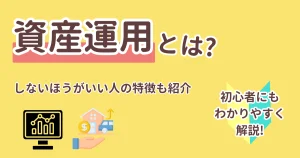

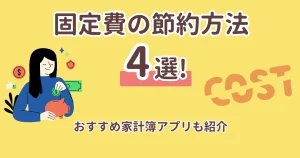
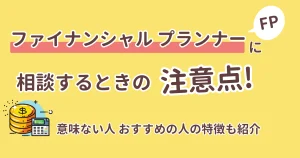
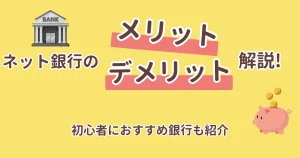
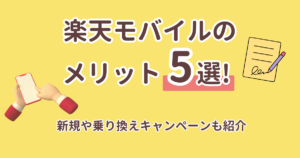
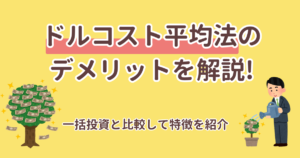
コメント